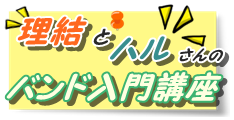本ページはプロモーションが含まれています。
55日目:演奏に凝れば凝るほど見えなくなるもの
ハルさん、すみませんー。。 先週のライブで、歌詞を一部間違えちゃいましたー。。。
あ、そうだったの? まぁ大丈夫じゃない? 曲の展開を間違えたり、演奏が大きくずれた訳じゃないんだし。
でもですよー。 せっかくのライブなんだから完璧な演奏をお客さんに聴かせてあげたいじゃないですか。。
うんうん。 それは全くもって良い心がけだね。 だけど、そこにこだわりすぎると見失ってしまうものがあるよ。
ライブで一箇所間違えてしまった!どうすれば・・・
ライブではミスを全く犯さずに演奏をするのは難しい。 機材や体調のトラブルもあるし、お客さんとのコンタクトや場の雰囲気に呑まれたり、汗でピックやスティックを落としたり・・・とかね。
だけど、実際問題、そのちょっとしたミスをお客さんが気づくことの方が全然難しい。 特にオリジナル曲の場合はなお更。
それはそうですけど、、、。
理結ちゃんがやってしまった歌詞の間違いも一箇所でしかも一緒に演奏しているメンバーが気づかないほどなんでしょ? そういうのはお客さんも気づかないし、気づいたとしても残念な気持ちにはならないと思うよ。 むしろ、そういうのを表情に出してしまうと、そのミスがバンドメンバーやお客さんに伝わって変な雰囲気になってしまう。
ミスのない完璧な演奏を目指すのはよいことだけど、ライブは想定通りに進まないこともよくある。 演奏を機械のようにこなそうとするより、ライブを楽しんでお客さんとの距離感に気を配るようにした方が良いよ。
ミスしても「そういう演奏です」で通す
だからもしミスをしても、演奏が止まってしまうような大きなミスでなければ流すようにしよう。 もちろん、顔には出さない。 「もともとこういう演奏です」と自分にも周りにも突き通そう。
そこでミスを悔いて動揺してしまうと、その後の演奏のパフォーマンスに大きく影響する。 だから「心で苦笑して泣いて悔やんで、表でポーカーフェイス」を心がけよう。
あ、確かにミスをすると思わず苦笑いしてしまう人も多いですよね。 私もだけど・・・(苦笑) これからは気をつけてみます。
音への過剰なこだわりはお客さんが見えなくなる
コピーでもオリジナルでも原曲や原案を一音の狂いもなく演奏させようとするバンドマンを見かけることがある。 確かに音へのこだわりがあるのはよい事だけど、行き過ぎてはいないだろうか?
あ、友達も言ってました。 オリジナルバンドをやっているだけど、メンバーにベースラインを一音一音綿密に指定されて憂鬱だって。 俺はただの演奏者かだって。
CDに録音するなら、ベースラインなどは一音一音しっかり決める必要が確かにあるけど、それはバンドメンバーで話し合って決めていくものだよね。 でもそういう細部に過剰にこだわることによって見えなくなる部分がある。 それが「音を楽しむ」ということだ。
楽しさがハイクオリティを生む
一つ一つの末端の音に気を使いすぎて、全体の曲調やバンドの雰囲気が冴えないものになることはけっこうありがちだ。 観客やリスナーにとって、細かな音の哲学よりも最初に聴いた時に気に入るかどうか。 いわゆるフィーリングが大きなウエイトを占めることを忘れてはいけない。
バンドをやっているとどんどん音にこだわるようになるし、それはとてもよいこと。 だけどそこに凝れば凝るほど深入りして音楽を楽しむことを忘れてしまう、いわゆる「音に溺れる」ことはないようにしたいね。 音楽は楽しんでやるのが一番だし、楽しんで向き合うことがハイクオリティを生むものだ。
◆まとめ
今回の講座『演奏に凝れば凝るほど見えなくなるもの』
- ライブではミスを全く犯さずに演奏をするのは難しい。でももしミスしてしまっても、ちょっとしたミスならお客さんが気づくことの方が全然難しい。
- 演奏を機械のようにこなそうとするより、ライブを楽しんでお客さんとの距離感に気を配るようにした方が良いライブになるはずだ。
- ミスをして顔に出したりすると、その雰囲気が周りに伝わるし、自分も動揺する。「心で苦笑して泣いて悔やんで、表でポーカーフェイス」を心がけよう。
- 聴く人が聴いた時に気に入るかどうかは、フィーリングが大きなウエイトを占める。楽しむことがハイクオリティが生むものなので「音に溺れる」なく音楽を楽しもう。